「よい牛」を、より速くより正確に生産するための科学
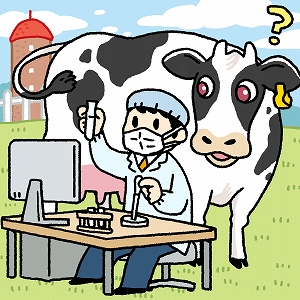
「ゲノミック評価」で牛の能力を数値化
農家の収入を上げるためには、経済能力の高い「よい牛」、つまり乳牛なら質のよい乳を多く出す牛を、肉牛なら肉質がよく肉量の多い牛を増やして「牛全体のレベル」を上げることが不可欠です。従来、泌乳能力、産肉能力および経験や勘に頼っていた「よい牛」の評価を、科学的に行う仕組みが「ゲノミック評価」です。乳牛の場合は乳量、体型、疾病・繁殖といった好ましい形質の遺伝子を、その個体がどれくらい持っているかを総合して数値で示します。子牛のうちに遺伝的な能力がわかり、効率よく「よい牛」を選べます。従来の経験に科学的なデータを組み合わせることで、より速く正確な改良が可能になります。
よい牛を増やすための受精卵移植
酪農では、オス牛よりもメス牛の方がより多く必要です。そのため、人工授精や受精卵を生産する際には「性選別精液」が使われています。メスになるX染色体を持つ精子とオスになるY染色体を持つ精子を、DNA量の違いで分けたもので、90%の確率で産み分けが可能です。優秀なメス牛の体内の受精卵を取り出して別のメス牛の子宮内に移植する「体内受精卵移植」も行われます。このとき安定した受胎率を確保するために重要なのは、ホルモン剤を使って、受精卵を提供する牛と移植を受ける牛の発情を同期化させることです。こうして遺伝的な能力の高い子牛が効率的に生産されています。
こうした高い技術と知識を持つ家畜人工授精師は非常に少なく、後継者の育成も大きな課題となっています。
地域内の循環をめざす
従来、家畜に多く与えていたのは、輸入穀物飼料です。しかし、今後輸入飼料に頼れなくなる可能性があり、国産飼料の確保は重要な問題です。現在、食品製造会社から出るビールや茶のかすなどの副産物を飼料に利用する「エコフィード」の研究が進められています。カギはこれらの副産物を発酵させて貯蔵性を高めるサイレージ化技術の開発です。地域で出た廃棄物を牛が食べて、その肉を地域の人が消費する、地域内循環が目標とされています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

酪農学園大学 循環農学類 准教授 西寒水 将 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
畜産学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標1]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-1-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )





