災害がきっかけの居住地移動 住まいの再出発を考える

避難生活で大切な、人とのつながり
地震や津波などの自然災害で自宅に住めなくなると、避難所や仮設住宅で生活することになります。阪神・淡路大震災では、近所の人たちがバラバラに避難したことで、もともとあった人間関係が途切れてしまい、高齢者の孤独死につながったことが大きな問題となりました。こうした教訓から、災害時には家族単位だけでなく、地域単位でまとまって避難し、その後も同じ仮設住宅や復興住宅に入居することが望ましいという考えが広がりました。人とのつながりは、心の支えや助け合いの力になるからです。
住まいの移動はマイナスなのか?
一時的な避難所や仮設住宅での生活の後は、本格的な住宅再建へと進みます。しかしこの段階になると、どこに住むか、どのように生活を再スタートさせるかは人によってさまざまで、地域のつながりがそこで分断されてしまうケースも多くあります。こうした人間関係の断絶はネガティブな面として語られることが多いですが、実は前向きにとらえる人がいることも、調査によってわかっています。例えば、2007年の能登半島地震では、山あいの過疎地から町へ移り住んだ人の中で「にぎやかで便利で良い」と話す人たちがいました。2004年のインド洋津波で被災したスリランカでは、それまでに経済的な理由で移動できなかった人たちが、災害をきっかけに新しい場所に移り住むことを「チャンス」と前向きにとらえているケースもありました。
より良い生活再建のために
災害後の居住地の移動が人々の生活にどのような影響を与えるのかを長期的に調べる研究は、これまであまり行われてきませんでした。しかし、被災者の声や生活の変化を丁寧に記録してデータを収集できれば、今後の災害復興政策に生かせます。あらかじめ幅広い選択肢を示すことができれば、被災者は自分に合った方法を選びやすくなり、不安も軽減できるはずです。災害に強く、人にやさしい社会をつくるために、こうした研究はとても重要な役割を果たすのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
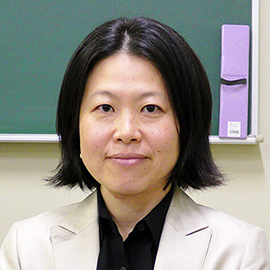
東海大学 文理融合学部 地域社会学科 法社会学 准教授 安部 美和 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
地域研究、復興政策先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )




