カギは「量」! 安全な医療のために放射線測定を究める
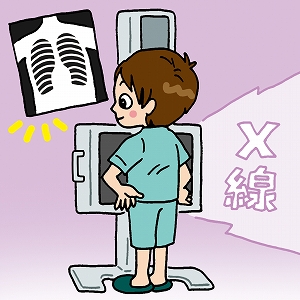
身のまわりにある放射線
放射線には生物の細胞を傷つける働きがありますが、少量なら浴びても問題ありません。私たちには細胞を修復する力があるからです。そもそも放射線はいつも身のまわりにあります。地面や建物から出ていますし、空気や食べ物にも含まれていて、実は人体からも放出されています。
しかし、細胞修復の力が追いつかないほど多くの放射線を浴びると、深刻な健康被害がおきるリスクがあります。放射線を使った検査や治療はいまや医療に欠かせませんが、安全のためには線量のコントロールが必要で、放射線計測の分野では医療現場で正確に線量を測定する技術の研究が行われています。
放射線医療機器のメンテナンス
レントゲン検査(X線検査)やCT検査は体の外からX線をあて、その通り抜け具合を画像にする検査です。検査機器から出るX線の量が適切かをチェックするため、例えば検査室内の空間線量を専用の測定器で調べますが、わずかな放射線を測るのは環境の影響を受けやすく不安定です。このため、より正確な測定法が研究されています。
放射線検査・治療機器のメンテナンスにおいても、線量を測定して、数値にエラーがないか知ることは大切です。そこで、機器のトラブルを防ぐために、蓄積した測定値からAIを使って故障の予兆を検知するアプリケーションの開発が進められています。放射線検査・治療のスペシャリストである診療放射線技師は、線量の測定や機器のメンテナンスを行い、安全な医療を守る専門家でもあります。
体内から出てくるγ線を測定
核医学検査は、体の中にγ線の放射性医薬品を投与して、体内から放出されるγ線を測定・画像化するものです。測定の間、患者は数十分動かずにじっとしていなくてはならず、測定の時間を短くして患者の負担を減らすことも研究目標の一つです。
放射線検査の進歩はめざましく、核医学検査とCTを合体させたPET-CT装置なども登場しています。その安全を支えるには、測定技術の進歩も不可欠なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
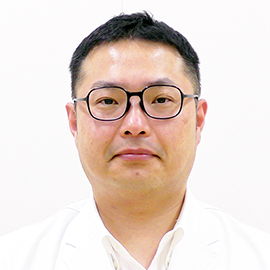





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
