身体の動かし方を通して、障害児の心の成長を促す

障害児が幸せに生きる未来をサポート
「特別支援教育」は、主に障害のある児童の教育を指します。身体に障害のある「肢体不自由児」の場合、身体(手・足など)の動かし方などを指導する「自立活動」という授業があります。その授業を通して、児童が身体の使い方や身体に対する注意の仕方を学び、徐々に立ったり歩いたりができるようになっていきます。
障害のある児童は、どうしても生活や学習の面で難しさを感じる場面が多いです。肢体不自由児は立ったり歩いたりという「運動動作」に関わるところが、他の障害のある児童は「コミュニケーションを取ること」「考えること」などが難しいという特性があります。それぞれの難しさは通常の授業ではなかなか対応できません。障害がありながらも幸せに生きる土台作りをすることが、特別支援教育のめざす先です。
「実態把握」が重要なカギ
障害のある児童への授業の際、その児童が何が苦手なのか、その苦手の背景は何なのか、教師がよく把握できないことがあります。特に児童とのかかわりに不慣れな教師の場合、よりその傾向が強くなります。そして、必要以上に勉強をするように詰め込みすぎたり、逆にその児童が必要な勉強を教えられなかったりすることもあり得ます。また、身体の不自由な児童の場合は、自立活動の授業などで無理な指導をした結果、けがをさせる可能性もあります。
教師は、よりよい授業をするために、児童の特徴(得意なこと、苦手なこと、身体の状態、気持ちの状態など)を、授業の前にしっかりと把握することが必要です。これを特別支援教育の世界では「実態把握」といいます。
身体だけでなく心の成長も促す
肢体不自由児の自立活動は、運動動作の学習がメインになりますが、児童には「身体の緊張」だけでなく「心の緊張」の状態を見つめる機会にもなります。「肩のあたりが固い」「思った通りに動かせない」「今日は楽に足が動かせた」などに児童自身が気づくことで、身体だけでなく心の安定も見込めます。それは「身体や心の成長を促す」ことにもつながります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
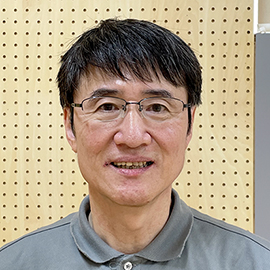
福岡女学院大学 人間関係学部 子ども発達学科 教授 堀江 幸治 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
特別支援教育、肢体不自由児教育先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )




