田んぼで暮らす生き物を守る 農業の効率化との両立をめざして

田んぼは魚の子育ての場
田んぼは稲を育てるだけの場所ではなく、ドジョウやメダカなどの小さな魚にとって重要な子育ての場でもあります。川では水の流れがあるため卵が流されてしまいますが、田んぼの静かな水の中では安全に繁殖できるのです。しかし、作業の効率化のために水路のコンクリート化や深掘が進むことで、魚が田んぼに入れなくなってきました。そこで考案されたのが「水田魚道」です。水路から田んぼへ魚がのぼりやすい階段状の構造を設けることで、田んぼを繁殖の場として再び活用できるようになりました。今では全国各地に広がっています。
複雑な生態系と保全の挑戦
農村生態工学の研究では、生物間の複雑な関係を理解した上で保全策を考える必要があります。例えば、絶滅危惧種となっているタナゴという魚は二枚貝に卵を産み、その二枚貝の幼生は別の種類の魚に寄生して成長します。つまり、タナゴは、二枚貝と二枚貝が寄生する魚が、同所に生息していなければ生き残れないのです。そこで、こうした複雑な関係を踏まえながら、ため池の造成やコンクリート水路内への泥だめ設置など、さまざまな保全策が提案され、農家の協力を得て実践されています。
農村の生態系保全の新たな課題
せっかく田んぼに魚がのぼれるようになり、ため池や水路で生きものを保全できるようになっても、外来種が捕食してしまうという問題が発生しています。中でも、生物多様性に大きな影響を与えているのがアメリカザリガニです。完全に駆除するのは難しいため、「低密度管理」によって被害を抑える方向で研究が進められています。例えば、わなから逃げにくいようにアタッチメントを工夫したり、メスのザリガニが産卵時期に巣に潜る習性を利用して、効率的な捕獲時期を特定したりといったことです。
農村地域の問題として、農家の減少や高齢化により、深刻な人手不足があります。農業のさらなる効率化と生物多様性保全の両立をめざして、地域の人々の理解と協力を得ながら研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
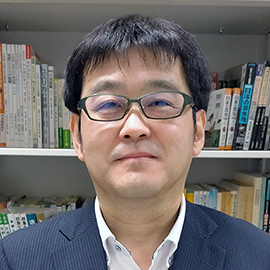
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )





