人間とロボットが共生する未来
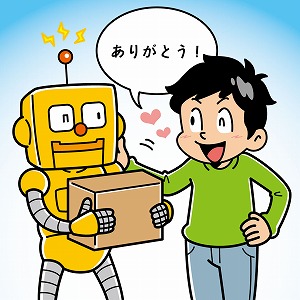
AIロボットの自己学習
現在、人間が作る道具はAI(人工知能)により自ら意思を持つようになっています。AIを組み込んだロボットを動かすと、ぎくしゃくした動きを繰り返した後、次第に滑らかに動くようになります。ロボットを設計した人は、どのモーターを駆動するとどの部分が動くかを理解していますが、ロボット自身にはわかりません。そのため、身体の中のモーターをランダムに駆動して動きを試しているのです。適当に駆動していると、その時の動きが自分の視野に入ります。自分の腕が動いているという視覚からの情報と、ある部分のモーターの駆動が時間的に相関したときに、その動作と駆動の関係を学習できます。もしも転がってきたボールが視野に入っても、体内のモーター駆動と相関しなければ、自分の動きと間違えることはありません。
ロボットを作ったあとは
ロボット自身が自分の体について学習した後、人間がロボットに物の動かし方を見せると、ロボットはそれを自分の基本動作として分析し、モーターの駆動順序を再構築します。知能は人間の生後10カ月程度のレベルですが、人間がプログラミングすることなくロボットは自己学習により動きを習得できるのです。そのため、人間が関わるのはロボット自体を作る工程までで終わり、そのあとは環境に合わせて、ロボット自身が最適な動きを考えて身につけていくのです。そのため、同じ設計で製造された数台のロボットが、数年後にはまったく違う動きをするものになっていることもあるでしょう。
人間とロボット
このように、AIを組み込んだロボットは自己学習を含めた自己制御、自己管理ができるようになりました。AIの判断によっては、人間が思いもしないような行動をとることがあるかもしれません。人間が生み出したロボットが人間の意思を超えてくる以上、人間はロボットの制御ではなく、調和のとれた共生を考えなければいけません。AIやロボットと共生することが、人間が次のステージに上がる鍵となるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

神奈川工科大学 情報学部 情報システム学科 准教授 三枝 亮 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
ロボット工学、情報工学、電子工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )

