「津波避難ビル」が安全であるために

災害の多い狭い国土
日本の国土は、地球の全陸地面積のわずか0.2%ほどに過ぎず、その中に世界で10位前後の人口である1億2000万人以上が暮らしています。そして近年、ある10年間でみるとマグニチュード6以上の地震の2割が日本で起き、台風の4割は日本に近づきました。非常に災害の多い狭い国土で、ひしめき合いながら安全に生活していくには、技術と知恵が重要です。
津波避難ビルの安全性
今後予想される南海トラフ地震のような巨大地震では、地震そのものの被害のほかに、津波による被害が懸念されています。近くに高台のない地域で避難場所として想定されるのが、建物の上階を利用する「津波避難ビル」です。
現在、建築基準法に沿った設計を行うことで、建物は一定の耐震性が確保されます。建物に横から力がかかるという意味では地震も津波も似ていますが、地震では地面が動いて発生する慣性力が作用するのに対して、津波では波の衝撃力です。建物の形状に対して波の来る向きや、波を受ける面の壁の有無によっても影響は大きく変わります。また、建物の立地条件にも大きく左右されます。木造建築が密集する立地の場合には、津波で破壊された建物のがれきが波とともに押し寄せるため、土石流のように水の重さが増して破壊力も大きくなります。建物の形状と立地が複雑に絡み合って波の力が変わるため、それらを細かく検証して津波避難ビルの安全性を確保するためのガイドラインを作るべきだと考えられています。
ハード面とソフト面
これらの検証は、模型実験による解析と、その結果をもとにしたコンピュータシミュレーションにより行われます。そして、こうした技術開発という防災のためのハード面が機能するためには、命を守る行動につなげるソフト面での研究も重要です。避難の意識を育てる教育や地域の防災活動を高めるために、地域住民の介入研究を行うとともに、官民学がタイアップした災害情報システムの構築をめざした研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
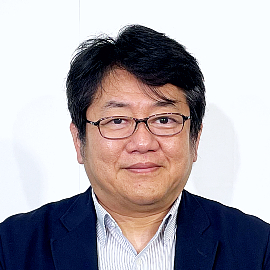
三重大学 工学部 総合工学科 建築学コース 教授 川口 淳 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
工学、建築学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )
