「リモートセンシング×AI」で自然保護活動に変革を
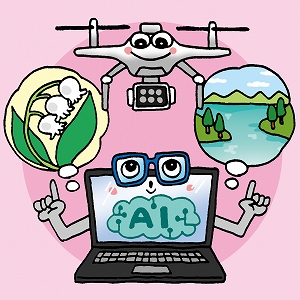
ドローンや人工衛星での撮影でデータ収集
遠く離れたところから、対象物に触れずに計測、観測する技術を「リモートセンシング」と言います。ドローンや人工衛星で、地上のものを撮影することもリモートセンシングの一つです。
リモートセンシングは、危険な場所でも観測できることや、「点」で観測するのではなく、一気に「面」で観測できる等のメリットがあります。その観測データをAIで解析することで、環境保護等に活用する研究が行われています。
リモートセンシングで自然環境調査
その一つが、希少な植物の調査です。通常は、人が実際にその植物の生育する場所に踏み入って調査しますが、人が踏み入ると周辺の環境に影響を与える場合があります。例えば、北海道のスズランの群生地では、ドローンで高さ2mから撮影した画像をAIで解析し、スズランの花の検出を可能にしました。これにより、人の立ち入り調査が不要となり、自然保護とその効率化が期待されます。
また、湖沼の水質状況把握に関する検討も行われています。秋田県の八郎湖調整池では夏にアオコが繁茂して水質が悪化し、水面が緑色になる問題があります。そこで、調整池を人工衛星やドローンから撮影し、AIを用いて画像解析することで、これまで把握が困難であった湖全体の水質状況把握が可能になりました。
対象ごとのカスタマイズが精度向上のカギ
画像の中にある特定の物体の検出や水質状況を把握するためには、大量にデータを与えて学習させる「機械学習」を使用します。
しかし、対象によってアルゴリズムのカスタマイズが必要になります。例えば、スマートフォンのカメラのように「人物の顔」を検出する場合と、「スズランの花」を検出する場合では、適切な学習データやアルゴリズムが異なります。これらのカスタマイズが検出精度向上のカギを握っています。機械学習による物体検出をはじめとするAIの技術は、自然保護活動以外にも幅広い分野で応用されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。







