「臨書」を通じた歴史と文化の追体験で、未来につながる表現を生む
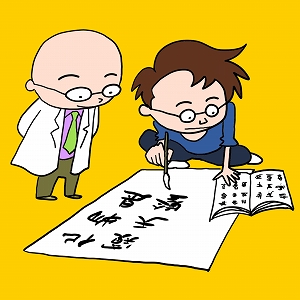
上手な字を書くだけじゃない
「書写と書道って何が違うの?」と思ったことはありませんか。中学校までの「書写」は、道具を使うことを覚えて文字の基本を学ぶ時間です。その基礎が定まったところで、「書道」では古典作品を学びます。
例えば、高校の書道の授業では「臨書」を学びます。臨書とは、古典作品の名筆を手本に、よく観察して忠実に書き写す学習です。先生の手本をまねる書写と同じ学習だと思うかもしれませんが、それ以上に、臨書から得られるものはたくさんあります。作品を書いたその人が、どんな角度で筆を入れたのか、またどんな気持ちで書いたのか、などを考えます。この学びには、作品を書いた人の立場になってみる「追体験」の意味合いがあります。
3000年超の歴史と文化が見える
書道の歴史は、3000年以上前の甲骨文字から始まります。古典作品は紙に墨で書かれたものばかりではなく、青銅器や岩に刻まれたものもあります。そうした作品を臨書する時、もちろん書かれている言葉や文章の意味も考えますが、なぜその場所に、どんな思いを込めて文字を刻んだのか、当時の状況にも思いを巡らせます。すると、当時の人々の暮らしや社会の様子が文字を通して見えてきます。時には教科書ではなく実物を見て、触って、作品の大きさや手触りから何千年も前の世界とつながり、追体験するのです。古典作品は豊かな情報の宝庫です。
臨書の学びが新たな表現を生む
臨書をすることで古典作品の技法を理解して、その精神性に触れ、文化的背景を知ることができます。書道は技術・文化・歴史などが複合的に織りなす総合芸術なのです。臨書学習を通じて、私たちは書の持つ多面的な価値に触れ、より深い芸術理解へと導かれます。そして重要なのは、これらの学びがあってこそアウトプットが可能になるということです。つまり、臨書は創作の基盤となります。古典から学んだ要素を自身の表現に取り入れて新たな表現を生み出していくという、書の歴史を未来へとつなげていく営みともいえるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

北海道教育大学 教育学部 教員養成課程(旭川校) 准教授 西川 竜矢 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
芸術実践論、教科教育学、書写書道教育学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
