交通デザインが開く持続可能なまちづくり
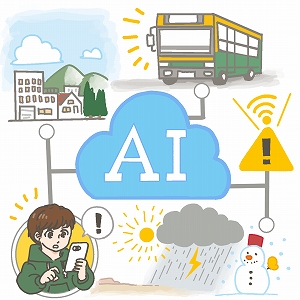
まちづくりの核となる交通インフラ
交通インフラは、まちの活力を支える重要な基盤です。交通は人々の移動手段であると同時に、地域の発展や生活の質を大きく左右する、まちづくりの核となる要素です。その重要性は日常の利便性にとどまりません。災害時の交通機能の維持は地域の安全にとって欠かせず、交通インフラが健全に機能することで地域全体の災害への耐性が高まり、住民の生活の質が守られます。
AI技術が開く新しい交通システム
富山県では、積雪時の交通の対策にAIを活用しています。路面積雪判定システムは、監視カメラの画像を解析してリアルタイムで状況を把握します。このシステムによって、住民やドライバーに危険な状況を事前に確認することで、ルートを選択できるようになりました。
さらに、富山のまちなかには、歩行者の交通量を測るAIカメラが複数台設置されており、歩行者交通量が年齢層別、性別ごとに24時間計測できるようになっています。このシステムを用いて、富山で行われるさまざまなまちの活性化の取り組みが、まちの賑わい向上につなっているかを分析でき、活性化策を検討することができます。
住民参加で築く持続可能な未来
持続可能な地域交通の実現には、先端技術と共に、住民の参画が欠かせません。住民参加型の交通の事例として淡路島の長沢地区という地域で運営されているミニバスがあります。この事例では、地域住民がミニバスの運転をしており、利用者のニーズを適切に反映した結果、多くの人に利用されています。加えて、地域全員でミニバスにかかる費用を支えています。このように協力し合って、公共交通を維持することが可能であることを示しています。
交通の維持は、日本全国で答えが出ていない問題です。難問だからこそ、技術革新と住民参加を組み合わせて、解いていかなければならない問題です。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

富山大学 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 准教授 猪井 博登 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
交通計画・交通工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?














