海藻が医療を変える? 藻類レクチンと糖鎖の特別な関係とは

「糖鎖」に結合するタンパク質
糖が鎖状につながった「糖鎖」は、核酸やタンパク質と並び生命現象にとって重要な生体分子です。糖鎖は主に細胞の表面に存在し「細胞の顔」として情報を担っています。例えばABO式の血液型は赤血球表面の糖鎖の違いによるものであり、インフルエンザウイルスは宿主細胞表面の糖鎖を認識・結合して感染します。また、正常細胞ががん化すると糖鎖構造に変化が生じます。
糖鎖に結合してその機能を発揮させるのが「レクチン」と呼ばれるタンパク質のグループです。レクチンはどの生物も持っていますが、特に藻類のレクチンは特定の糖鎖に特異的に結合する性質があるので、がんの早期発見やドラッグデリバリーなど幅広い応用が期待されます。
がんの検出やウイルス除去にも効果
藻類レクチンの研究では、海に潜って採取した海藻を仕分け、レクチンを抽出し、構造を解析してその機能を調べます。これまで、がんの転移に関係する糖鎖に結合するレクチンや、肝がんやすい臓がんの腫瘍マーカーに結合するレクチンなど、さまざまな特異性を持つレクチンが海藻から得られています。新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス、HIVウイルスなどの膜にあるスパイクタンパク質は特徴的な糖鎖に覆われており、この糖鎖に特異的に結合する藻類レクチンもたくさん見つかっています。
健康食品素材としても期待
HIVウイルスに結合するレクチンを利用して開発された透析デバイスは、試験液に含まれるウイルスを99.9%以上除去することに成功しました。レクチンはウイルスの糖鎖に結合し、ウイルス同士を凝集させて感染力を失わせます。将来的には抗ウイルス薬としても活用できるかもしれません。
また、刺身のつまに使われるトサカノリのレクチンには、培養細胞を使った実験で大腸がんを抑える作用が確認されています。このレクチンの特徴は消化酵素への耐性で、食べれば消化されずに腸まで届くと考えられるため、健康食品素材としての利用が見込まれています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
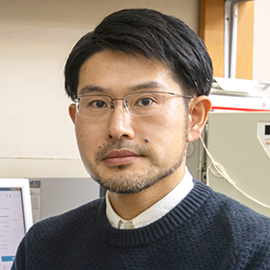
広島大学 生物生産学部 生物生産学科 食品科学プログラム 講師 平山 真 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
水圏生命科学、糖鎖生物学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )






