統合失調症に多い「結論への飛躍」とは? 原因と治療方法を探る
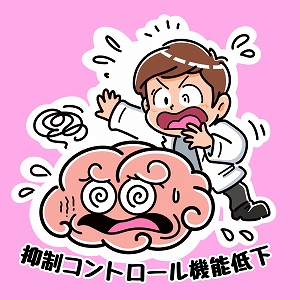
統合失調症に多い認知バイアス
統合失調症は、約100人に1人が発症する比較的身近な精神疾患です。その半数以上の患者に見られる特徴として、少ない情報ですぐに決めつけてしまう「結論への飛躍」という認知バイアスが挙げられます。臨床現場ではよく観察されるのですが、標準化された検査や治療方法はありません。それどころか、原因もまだ明らかにされていません。
結論への飛躍を測るビーズ課題
そこで、結論への飛躍を測るために、「ビーズ課題」という検査が作られました。ビーズ課題では、2色のビーズを2つの容器に逆の比率に入れたものを用意します。例えばAの容器には赤いビーズが80個、白いビーズが20個、Bの容器には逆の比率でビーズが入っており、そのことを被験者は知らされます。次にどちらの容器かわからないようにして、片方からビーズを一つずつ取り出して被験者に見せます。被験者にはAとBどちらの容器からビーズが取り出されていると思うかを答えてもらいます。
統合失調症ではない被験者の場合、ビーズを10個ほど見たタイミングで結論を出しました。一方、統合失調症の患者は3個程度で答えています。答えへの確信度にも違いが出ており、統合失調症の患者は1つ目のビーズの時点で高い確信を持っており、その後も確信度はあまり変わりません。少ない情報で判断を下す、結論への飛躍の特徴が出ているといえます。
「結論への飛躍」が起こる原因は?
さらに、ビーズ課題の結果と、統合失調症の精神症状や脳の前頭葉機能を測る検査との関連を調査したところ、結論への飛躍をする人の共通点が見えてきました。一つは脳の抑制コントロール機能の低下です。そのため情報をある程度集めて吟味する、といった行動が苦手になっていました。もう一つは意欲の低下です。情報を集める意欲が低下しており、早い段階で結論を出そうとしてしまうのです。
これらが原因となって結論への飛躍が起きている可能性を踏まえ、治療やリハビリの方法を提案しようと研究が続いています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
