地域を元気にする「イノベーション」は起こせる!
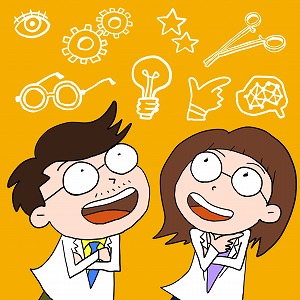
「地域イノベーション」とは?
地域イノベーションは地域や産学官の関係、空間スケールなどを研究対象として、どのような条件下でイノベーションが起きやすいのかを分析します。そのため、経済学と地理学の境界部分にある「経済地理学」や、産業や工業の立地を扱う「立地論」とは切っても切れない関係にあります。
3種に分けられるイノベーション
地域イノベーションは3つの類型に分けられます。一つ目は「サイエンス系イノベーション」といい、大学の研究成果を企業が事業化したり、製品化したりすることで生まれるイノベーションです。この場合、大学の研究成果は言語化された「形式知」としてグローバルに行き交います。具体的には、京都大学のiPS細胞の研究成果が製薬企業に提供され、再生医療の創薬に役立てられている例などが挙げられます。
二つ目は「感性系イノベーション」で、ひらめきから生まれるクリエイティブなイノベーションです。どのような環境でひらめきが生まれるのか、客観的なデータによって実証することは困難ですが、東京の渋谷のようなクリエイティブな人やアイデアが集まる場所や、自然豊かな環境がインスピレーションの源泉になる傾向があります。
福井県はものづくり系イノベーションが盛ん
そして三つ目が、特定の地域において、中小企業と公設の試験研究機関などが連携して起こす「ものづくり系イノベーション」です。この場合、中小企業が持っている技術は言語化されておらず、技術者と一体化している「暗黙知」です。そのため、「形式知」のようにグローバルにやりとりはできず、対面接触で試行錯誤を重ねながら伝達されます。
例えば、福井県はまさにものづくり系イノベーションが盛んなエリアです。全国的に眼鏡フレームの製造で知られていますが、それだけに留まらず、チタン合金の素材と加工技術を生かし、医師が使用するピンセットやはさみなどの手術具にも挑戦しています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
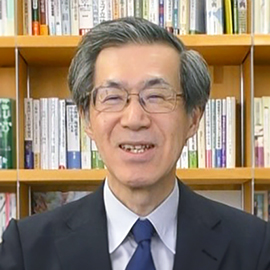





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
