微生物活用で水田のメタン排出を抑え、持続可能な米作りを
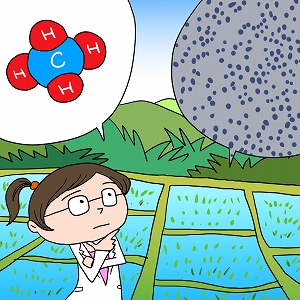
微生物を活用したメタン排出量削減
メタンは、二酸化炭素よりも温暖化能力が28倍も高い温室効果ガスです。ただし、大気中に滞留する時間は二酸化炭素と比べて短いため、排出さえ抑えれば、温暖化抑制の即効的な対策となり得ます。
米が主食の日本では、人為的なメタン排出量のうち約半分が水田から排出されています。水を張って酸素が入りにくくなった水田の土壌では、「メタン生成古細菌」と呼ばれる微生物が有機物からメタンを生成し、イネの通気組織を経由して、あるいは水田から直接泡として排出されるのです。一方、土壌やイネの根の周辺および内部に生息する「メタン酸化細菌」は、メタンを唯一の炭素源・エネルギー源とし、それを二酸化炭素と水に分解します。このメタン酸化細菌を活用して、水田のメタン排出量を削減しようという研究が行われています。
難しいメタン酸化細菌の分離
その一つがメタン酸化細菌の分離です。メタンのみを炭素源・エネルギー源とした培地を用いてメタン酸化細菌を分離するのですが、最も難しいところはメタン酸化細菌の代謝物をえさとするほかの細菌を取り除くステップです。何回も培地を希釈して顕微鏡で確認し、メタン酸化細菌だけを分離する高い技術と経験が必要です。分離されたメタン酸化細菌は、さらに有用な菌の絞り込みをめざして、ゲノム配列や生育条件、農業に応用する際の使いやすさなどの性質が調べられています。
メタン酸化細菌の活用
多くの人に好まれるコシヒカリは、メタン排出量が多い品種です。そこで、コシヒカリに代わるような似た食味で、「メタン排出量の少ない品種の普及」を目的として、そうした品種のイネの根に生息するメタン酸化細菌の特徴が研究されています。さまざまな品種の根からDNAを抽出して調べることで、メタン排出量の少ない品種の根に多く存在する菌の種類や量が明らかになってきました。
これらの研究成果は、高活性のメタン酸化細菌を使ったイネの微生物資材の開発や、メタン酸化細菌の活性を上げる栽培方法などへの応用にも期待されます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。





![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )



