教科を超えて知識と体験をつなげ、社会が共有する科学リテラシーを

広がる理科の学び 〜電池を例として〜
例えば「電池」という言葉は、物理・化学・生物・地学すべてに登場します。物理では電流と電圧の関係(オームの法則)を学び、化学ではレモン電池などによる発電、生物では神経細胞の活動を、地学では地球が電流を生み地磁気を作る仕組みを扱います。このように、理科の複数分野を横断しながら理解を深めることができます。
歴史をたどれば、オームの法則は電圧計のない時代に生み出され、ボルタ電池は動力源として生み出されたわけではありませんでした。屋井乾電池は画期的な技術革新でしたが、乾電池のすごい点はどこでしょうか。身近な概念に広がりをもたせて考える姿勢は、理科の一つの核といえるでしょう。
教科横断の中で見る理科
近年、高校で必修化された家庭(科)と情報に注目してみましょう。
研究からSDGsに最も深く関わる教科として家庭(科)が示されるのですが、SDGsが課題とする環境・福祉・人権などの理解には理科・社会・数学との連携が欠かせません。
情報も必修化され、ほぼ全員がプログラミングや情報リテラシーを学びますが、これらは手段であり、目標達成のために他の分野の知識やツールと関連付けられて力を発揮します。
理科は「モデル化」や「仕組み化」を通して、教科横断的な思考に寄与する教科です。
科学リテラシーを育む大切さと、取り組み
知識と体験の共有される関連付け=リテラシーは、協働社会の基盤となります。理科はこれを育てる教科ですが、柔軟な応用力は理科だけでは補えません。
現在、Web上の語の関連を可視化する研究を通じ、これらの言葉の関係性から、社会が共有すべき科学リテラシーの在り方を明らかにする取り組みが行われています。
理科の実験は人間の科学リテラシーを育みますが、学校現場ではその機会が減少しています。子どもに科学体験を届ける活動は、科学リテラシーの更新にもつながる努力でもあるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
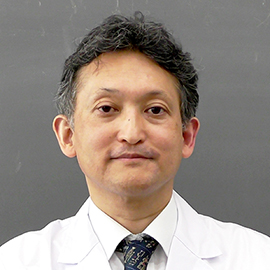
秀明大学 学校教師学部 教授 田中 元 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
生物無機化学、化学教育、理科教育先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )




