生糸の生産だけではない! 農薬開発におけるカイコの活躍

農薬研究にも役立つカイコ
養蚕(ようさん)で知られるカイコは、生糸の生産のほか、農薬などの研究にも役立っています。飼育のノウハウが確立していることや、ゲノム解読が完了していることなど、カイコには研究上のさまざまな利点があるからです。また、農作物に甚大な被害を与える芋虫型の昆虫と非常に近い遺伝子を持っているため、農薬分野におけるモデル昆虫としても重宝されています。カイコに作用する農薬は、ほかの害虫にも効果を発揮するのです。
虫を殺さない農薬作り
農薬を使わなかった場合、作物の生産量が減ったり質が下がったりといったリスクがあります。そのため安定的な食料の供給に農薬は欠かせません。しかし、害虫を即座に殺すような薬は、人の健康も損ねてしまう恐れがあります。また、虫がだんだんと抵抗性を身につけて、農薬の効き目が弱まってしまう点も問題視されています。
一方で、虫の行動を制御するタイプの薬は、抵抗性が上がりにくいことがわかっています。そこで、より安全で長く使える農薬を開発しようと、餌を食べる「摂食行動」を制御する実験が、カイコを使って行われています。
摂食行動を制御する
摂食行動は、脳の神経から発せられたシグナルを伝達物質が運び、それを受容体タンパク質(レセプター)が受け取ることで生じます。カイコの摂食行動に関係する伝達物質とレセプターがわかれば、薬でその働きを制御して農作物への被害を抑えられるでしょう。候補として挙げられるのが、神経物質の伝達に役立っている「生体アミン」です。
生体アミンにはアドレナリンやドーパミンなどさまざまな種類があるため、どれが摂食行動に関係しているか特定する必要があります。いくつもの生体アミンをカイコに与えて、餌を食べる量の変化を観察したところ、ドーパミンと5種類のレセプターが関係していることがわかってきました。各レセプターの機能をさらに解明して、虫が農作物をあまり食べないようにする薬を作ろうと研究が続けられています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
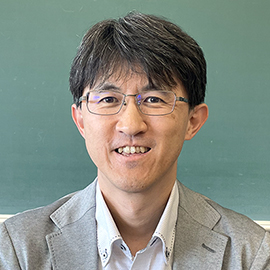
崇城大学 生物生命学部 生物生命学科 教授 太田 広人 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
昆虫神経生理・生化学、農薬化学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )





