空気中の酸素も使う! 次世代の蓄電池に使う材料を探索
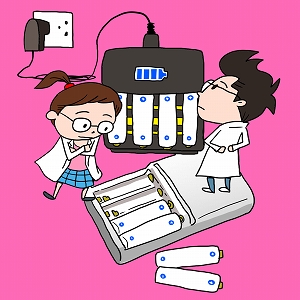
リチウムイオン電池の課題
スマートフォンなど、身の回りの多くの機械にはリチウムイオン電池が使われています。これは、使い捨ての一次電池とはちがって、くり返し充電して使える二次電池(蓄電池)です。電気をたくさんためることができて、安定して使える便利な電池ですが、まだ多くの改善の余地があります。たとえば電気自動車は1回の充電で数百km走れますが、そのために200 kg以上の電池が必要です。電池が重いと燃費も悪くなるため、もっと軽くて容量の大きい電池が必要とされています。
ガラスを電池の材料に!
もっと軽くて容量が大きい電池を目指し、新しい材料の研究が始まりました。中でも、注目されているのは酸化バナジウムを主成分にした「ガラス材料」です。ガラスは、見た目は固体なのに、中の構造は液体のようにバラバラというユニークな性質を持っています。この特性を活かして、2種類の電池材料が開発されました。1つ目は、リチウムイオン電池の正極(+)に使う活物質です。電池容量は、正極や負極にある活物質の性能で決まります。2つ目は、次世代の電池として注目される「金属-空気電池」の空気極(+)に使う触媒材料です。この電池は空気中の酸素を活物質として使うので、電池を軽くでき、容量も大きくなります。ただし、くり返し使うには、酸素の反応を助ける「触媒」という材料が必要です。
多彩な構造 × ドーピングで性能アップ!
このガラス材料を使った次世代電池の研究が進んでいます。液体のように構造が自由なガラスは、多彩なかたちをとれるのが強みです。リチウムイオン電池の正極材料では、この性質を活かして電子やリチウムイオンをたくさんためられるように工夫され、容量が従来の2倍以上に向上しました。さらに、特定のはたらきをもつ不純物をわずかに加える「ドーピング」により、材料の弱点を補い、性能がさらに向上します。金属-空気電池の空気極の触媒でも、ガラスの構造とドーピングの効果を組み合わせて、より高性能な次世代電池の開発が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )






