地球への帰還を安全に! 危険な大気圏突入を地上で再現
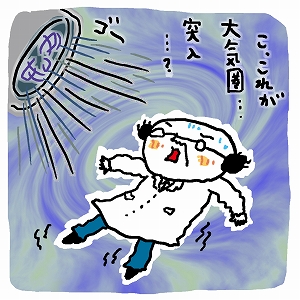
解決が急がれる宇宙技術
小惑星探査機「はやぶさ」は過去に2回、天体のサンプルを採取して地球に持ち帰りました。今後も、そうした計画は次々と予定されています。世界全体でも探査機や宇宙ステーションなどから分離されて地球へ帰還したカプセル型宇宙機はたくさんありますが、実はまだ、100%無事に帰還させる技術が確立されているとは言い切れません。
大気圏に突入する際、空気抵抗など気流の影響によって帰還カプセルは激しく振動することがあるといわれています。もしそうなると、場合によってはパラシュートがうまく開かないなどの危機に直面する懸念が残っているのです。
シミュレーションに成功
カプセル振動がなぜ不安定になることがあるのか、そのメカニズムは謎に包まれています。解明するには、大気圏突入の際に何が起きているのかをリアルに再現することが必要です。
複雑で難易度は高いものの、流体力学や飛行力学などを駆使し、シミュレーションによる再現に成功しています。シミュレーションにより、カプセルまわりの高い周波数の乱流と、それよりも低い周波数のカプセル振動が複雑に絡み合っていることなどが少しずつわかってきました。
画期的な実験装置で明らかに
安全性の確立には、実験でも立証する必要があります。シミュレーションと実験で再現して初めて、信頼できる改善策を立てられるからです。実験には、人工的に気流を発生させて、物体に働く力やそのまわりの空気の流れを計測する「風洞」という装置を使います。従来の風洞は、縮尺模型を固定したものや、模型をプログラムどおりに動かすものが主流でした。そんな中、空気の力で模型が自由に動く、より実際に近い状態を再現できる風洞が開発されました。磁力を巧みに使って実現されています。これは、JAXAや宇宙開発関連企業も注目する独自の技術です。
風洞による大気圏突入の再現が完成すれば、安全への検証が大きく進みます。安全性の向上は、今後の宇宙開発に大きく貢献するはずです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。







