その家具は誰が作った? 地場の産地を通して知るモノの価値
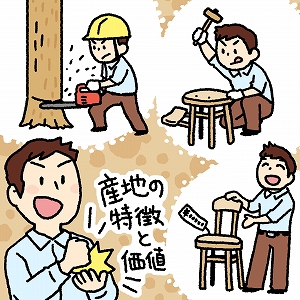
産地を知る
現在、国内の家具市場は大型量販店が高いシェアを誇り、そこで売られる家具の多くが外国産ですが、日本にも家具産地があります。その一つである旭川地域では、北海道産の木を使ったり、北欧風のデザインを取り入れたりして、産地としての特徴を打ち出すことに成功し、若者の参入も増加しています。
実際に作ってみる
同じく、静岡県中部にも大きな家具産地があります。近くには東京や名古屋という大消費地があり、製造から販売まで多くの業者が集まっていますが、産地の特徴という意味では、見えにくい地域です。家具産業全体が縮小傾向にある中で、産地としての特徴が見えにくければ、将来的に産地の弱体化につながる可能性もあります。
静岡産地が特色を打ち出すために解決すべき課題は、理論や知識を学ぶだけでは見えてきません。例えば木の産地に足を運び、林業の人たちと一緒に木を切ってみたり、家具を作ってみたり、販売してみたりと、材料の産地に身を置いて、生産から流通までのプロセスを実際に経験することで、初めて気づけることもあります。これまでの調査で、静岡産の木がほとんど使われていないことがわかっています。また材料の調達や加工、流通、販売、そして行政と、それぞれの役割が専門分化しすぎているために、家具産地の中のつながりが薄いこともわかってきました。
地域産業に目を向ける
経済の動きには、実に多くの要素、組織、人が絡むため、マクロ的な広い視点をもつことが不可欠です。しかし、そうした広い視野をもつためには、地場の産地を含めて、生活に最も身近な地域の経済に目を向けることが重要です。家具産地であれば、誰がどんな思いで作ったのか、どんな材料が使われているのかなど、その産地ならではのストーリーが見えてきます。そうしたストーリーが価格やスペックでは表せない価値を生み出して、消費者の選択を変え、それによって地域の産業がより持続可能なものになるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






