幼児と小学生の生物の世界をつなぐ研究
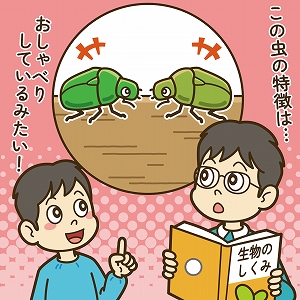
素朴生物から学校生物へ:子どもの概念の発達
子どもたちは、日々の観察や体験を通して、自分なりの考えをつくりあげていきます。たとえば、「虫がおしゃべりしているみたい」といったような、生き物についての自然な思い込みをすることがあります。こうした考え方は、まだ科学的な知識がない段階で生まれるもので、「素朴理論」と呼ばれます。特に、生き物に関する素朴な考え方は「素朴生物」と呼ばれ、幼稚園や保育園の子どもたちはこのような世界で生き物とふれあっています。しかし、小学校に入ると、理科の授業で「生物のしくみ」や「科学的な見方」を学ぶようになります。これを「学校生物」と言います。
「不思議」が「科学」に変わるとき
子どもにとって、「ふしぎだな」と感じる気持ちが、やがて「科学的な理解」へと変わっていくのは、いつ頃なのでしょうか。これについて、3歳から5歳の幼稚園児を対象に、イラストを使った調査が行われました。「このコーヒーカップは、大きく成長すると思う?」「黒い目の太郎くんは、大きくなったら青い目になれるかな?」といった質問です。これは、子どもたちが「生き物」と「無生物」を区別できているか、また「人の特徴」についてどれくらい理解しているかを調べるものでした。その結果、正しく答えられた割合は、3歳児で約3割、4歳児で約6〜7割、5歳児では8割にまで上がりました。このことから、年齢とともに子どもたちの理解力は伸びていく一方で、すべての子どもが科学的な知識の土台をしっかり持っているわけではないこともわかりました。
幼・保・小の接続をスムーズに
現在、子どもたちの「科学への興味・関心」を積極的に育てようと意識している幼稚園教諭や保育士は、まだ少数派です。そのため、幼児期に育まれた「素朴な生き物観」から、小学校で学ぶ「科学的な生き物の見方」へと、子どもが自然に移行できるようにするには、幼稚園・保育施設と小学校の教員同士がもっと交流し、お互いの教育内容や子どもたちの育ちの様子を理解し合うことが大切です。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

宮城学院女子大学 教育学部 教育学科 幼児教育専攻 准教授 伊藤 哲章 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
幼児教育学、生物教育先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?






