コメの収量と品質を高める! ドローン診断と品種改良
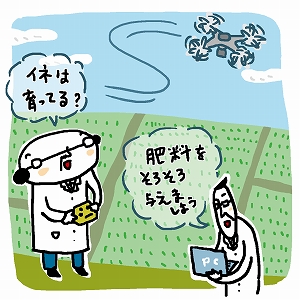
ドローンを活用してコメの品質向上
昨今の夏の暑さはコメの品質にも大きな影響を与えています。一部が白くなった米粒、「白未熟粒」を見たことがあるでしょうか。米粒の透明な部分にはデンプンがぎっしりと詰まっていますが、白く濁った部分は隙間があり、割れやすくなるのです。米粒の中のタンパク質が不足すると、白未熟粒となることがわかっています。タンパク質を作るためには、窒素が必要です。しかし、タンパク質が多すぎるとコメの味が悪くなるため、ちょうどよい量の窒素肥料を与えなくてはなりません。そのために、ドローンを使って上空からイネの栄養状態を診断し、適切な肥料の与え方を提案するシステムの構築が研究されています。ドローンによって精度の高い診断ができるようになれば、暑い夏でもコメの品質維持に役立つ可能性があります。
実りをよくする品種改良でコメの多収化
未来の食糧の確保のためにコメの収量の向上が不可欠です。収量とは単位面積当たりの収穫量のことで、コメの収量向上のためには1つの穂に多くの籾をつけることが必要です。ただし、籾数を多くすると実りが悪くなるため、実りをよくする品種改良が必要になります。イネにはインディカ型とジャポニカ型があり、インディカ型は籾数が多くてもよく実る傾向にあります。インディカ型の品種から実りに関する遺伝子を見つけて、ジャポニカ型の品種に導入し、多収品種を作る研究が進められています。現在、実りに関する遺伝子について、染色体上のおおよその位置がわかってきました。
コメ多収のためにもドローンは役立つ
コメの収量を高めるためには栽培管理も重要です。例えば、それぞれの品種の実りの能力に応じた適切な籾数をつけることがあります。籾数はイネが吸収した窒素の量で決まるので、窒素肥料によって調節が可能です。ドローンによる診断に基づいた籾数の調節技術の構築が研究されています。
このように、コメの品質と収量を向上させるために、栽培管理や品種改良など、多方面からの研究が進んでいます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






