現代メディアの課題、その向き合い方を歴史に学ぶ
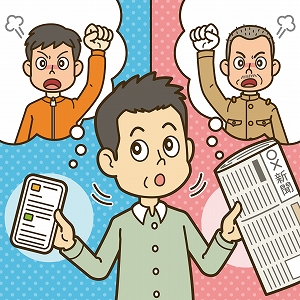
ネット社会の問題点は現代特有のものではない
私たちは、情報ネットワークと生活が結びついた「インターネット社会」の中で生きています。インターネット上でのコミュニケーションは、情報の正しさや理性的な議論よりも、好きか嫌いかといった感情的な意見による議論が行われがちです。しかしこうした状況は、決して近年になってから生じたわけではありません。明治から昭和にかけての近代日本でも、相手を排除しようとする攻撃が高まる中で、議論が政治的に利用され、問題がメディアを介して世の中に広がるなど、現在と類似する状況が起こっていました。メディア史やジャーナリズム研究では、新聞や雑誌などを調査分析して、当時の政治状況や社会的出来事と現代の問題を絡めながら考察を行います。
感情的な議論が引き起こした事件
昭和初期に起こった「天皇機関説」問題は、戦前の天皇の位置づけや政治的な役割をめぐって感情的な議論が先行した一例です。天皇機関説とは、主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治するという学説で、美濃部達吉が代表的な論者として知られています。天皇が絶対的な権力を持つのではなく、憲法に基づいて統治を行うという主張を、軍部や右翼は不敬とみなして美濃部を攻撃しました。ジャーナリズムを用いて美濃部を批判するキャンペーンを展開したのです。その結果、彼は貴族院議員の地位を退くこととなってしまいました。
過去の研究から現在を学ぶ
現在の民主主義社会は危機に瀕し、世界中でさまざまな問題が勃発しています。こうした状況の中で、私たちはいかに生きればよいのか、社会の問題に対してどうすればよいのかを考える上で手がかりを与えてくれるのがジャーナリズム研究です。現代の問題に直接アプローチするだけではなく、さまざまな出来事を歴史的な視点から分析し、その知見や研究成果を現代の問題につなげて考察します。歴史的なアプローチから現代の問題に迫ることが可能なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )

