電気が止まっても生き延びる! 災害時に重要なオフグリッド建築
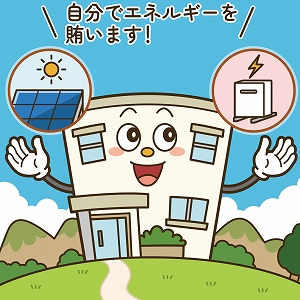
災害に強い建物を造る
例えば南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、高知県では支援が届くまで市内でも1週間、山間部では2週間以上かかる可能性が指摘されています。そのため被災直後から自立して生活できる体制を整えておくことが重要で、電気や水、ガスといったライフラインの確保が鍵となります。そこで注目されているのが「オフグリッド」という考え方です。これは、企業の送電網などに依存せず、太陽光発電や風力発電、蓄電池などを活用して建物が自力でエネルギーを賄う仕組みで、万一送電網が止まったとしても、生活を続けられるようにする工夫です。
診療所を災害拠点に
高知県西南部のある町では、津波発生時の避難所として、山の上にある古い診療所を災害拠点にする計画が進んでいます。この診療所のオフグリッド化に向けて、太陽光発電や蓄電池の導入に加え、建物自体の断熱性能も高める取り組みも行われています。昭和時代に建てられた古い建物のため、断熱性が低く、空調の効きが悪いという課題があります。せっかく発電しても、熱が逃げやすい建物では効率がよくありません。さらに災害拠点としては、薬品の保存のために一定の温度管理が不可欠です。こうした問題を解決するために、建物の断熱性能をシミュレーションし、断熱材を追加するなどの改修が検討されています。
未来のまちを守るため
オフグリッド建築の考え方は、災害対策に限らず、将来のまちづくりにも役立ちます。日本では人口の9割以上が都市部に集中しており、国土の6割は過疎地域です。戦後に急速な都市化を経た日本では、今後50年の間に、インフラや建物の老朽化によるメンテナンス需要が一気に高まると予測されています。特に地方部では、人手不足から対応が難しくなる可能性があります。そうした状況の中で、送電網に頼らず自立できる建物は、地域の暮らしを支える大きな力になります。持続可能な暮らしをめざす上で、オフグリッド技術の研究は今後ますます重要になります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

高知工科大学 システム工学群 教授 木多 彩子 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
地域施設計画、住環境デザイン、建築企画先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

