うつ病の治療薬で「神経細胞が若返る」ってどういうこと?
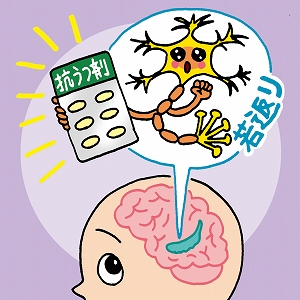
解明されていないメカニズム
「海馬」と呼ばれる脳の部位は、学習や記憶の保持などに関わりがありますが、うつ病の治療薬の標的としても重要であるなど、精神疾患の病因・病態にも関連があります。うつ病は脳内の情報伝達を担うセロトニンなど神経伝達物質の機能異常が関連しているといわれていますが、脳内で何が起きているかといった発症のメカニズムは明らかではありません。その治療薬についても、神経伝達物質の濃度を上げる効果などは確認されていても、実際の作用メカニズムまではわかっていないのです。
細胞レベルの変化を観察
そこで、うつ病の治療薬を使って海馬の神経細胞レベルで起こる変化を調べる実験が行われました。マウスに一定期間抗うつ薬を飲ませてから、神経細胞が生きたままの状態で脳の切片を作ります。個々の神経細胞の電気活動を記録し解析すると、本来起こるべき電気活動とは異なる顕著な変化、つまり細胞機能の変化があったことが確認されました。神経細胞には前駆細胞から分化して若い神経細胞になり、その後成熟するという長い過程がありますが、抗うつ薬を飲ませたマウスの神経細胞の機能は若い細胞に似ていました。機能以外の解析結果も合わせて考えていく中で、成熟していた細胞が抗うつ薬によって未成熟に戻る、つまり見かけ上の若返りが起こっているという結論にたどり着きました。
「成熟度が変わる」という新しい見方
これまで若い神経細胞から成熟した細胞になるまで一方向に進むと考えられていましたが、先述の研究で「成熟度が変わる」という新しい見方が生まれました。その中では、おそらく健康な脳でもさまざまな刺激によって成熟度が逆戻りし、再び成熟が進むということを繰り返しており、精神疾患の場合は、この逆戻りに異常が起きると考えられています。
この細胞レベルの新しい見方は、すぐに治療に結びつくわけではありません。しかし、細胞の成熟度や脳の病気、薬の作用メカニズムがさらに解明できれば、薬に頼らない治療や病気の予防ができる可能性があります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。







