工学と情報学とを融合したエンジニアを養成する教育とは?
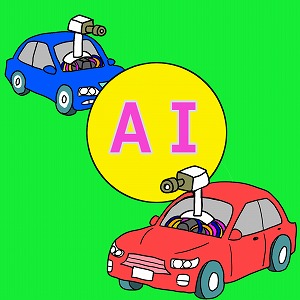
工学と情報学を兼ね備えた技術者養成
AIは人間をはるかに超える情報処理能力があり、さまざまな機器を制御することで高い性能を持つ製品が開発できます。例えばモビリティ(移動)であれば、センサで周りの状況を把握し、その情報をAIが瞬時に分析、対応することで、安全性、快適性が格段に高くなります。
AI制御機器の開発には、機械部品と、センサ・モータなどの電子部品からなるハードウェアの性能と、AIプログラムの両方が必要です。これは、メカトロニクスとソフトウェア制御が統合された「工学」と「情報学」が融合した製品といえます。このような製品を開発するためには、工学の知識と情報学の知識を兼ね備えた技術者養成のための実践的な研究が、今、特に注目を集めています。
実践的な学習教材
そうした研究の中で、工学と情報学を同時に学べる、自動運転技術学習支援教材が開発されました。センサとモータなどで構成された機器が学生一人一人に割り当てられ、それを動かすプログラムを学生が作るのです。この教材は、自動運転に必須の「環境センシング」「行動生成」「車両制御」の技術を統一的に学べ、ロボットやメカトロニクスの学習にも応用できるもので、「KaitCV」と名付けられました。実際にモノを動かしてみることで、座学では得られない実践的な力が身につくのです。
自動運転車のレースでの「現場対応力」
工学と情報学を同時に学べる実践の場として、自動運転車のレースが有効であることがわかっています。市販のRCカーにマイコンを搭載した車両を用いて、データ収集・教示・パラメータチューニングにより、その走行挙動を調整したAIによる自動運転でコースを周回させ、周数を競うレースです。競うことで学習へのモチベーションが上がり、かつ、結果が明確に出るため、問題点を具体的に把握できます。開発やビジネスの現場では、想定外の出来事がつきものです。レース中のアクシデントを経験していく中で、知識だけでなく、問題に向き合う「現場対応力」も身についていくのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

神奈川工科大学 工学部 機械工学科 助教 小宮 聖司 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
設計工学、知能情報システム先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )


