希少な症例でも対応 PET検査の負担を減らすAI画像処理
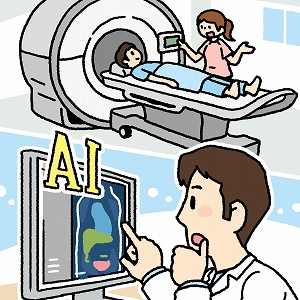
体内の機能を測定するPET検査
病院での画像診断の一つに「PET検査」があります。放射線を出す薬を注射し、体内への薬の広がり方を画像で撮影する方法です。PETは、CT・MRIのように臓器の形を見るものではなく、注射した物質がどこに運ばれ、どのように代謝されているかといった臓器の機能を見るものです。例えば、がんがあるところにはブドウ糖がたくさん集まります。放射性のブドウ糖を注射して撮影すると、放射線量が高く表れている部分が写り、がんの位置が正確にわかるわけです。
しかし、安全な量とはいえ、患者や医師、介助者も放射線の被ばくのリスクがあります。また、場合によっては動脈からの採血が必要など、さまざまなリスクもあります。そこで、AIの画像処理で、この負担を減らそうという研究が行われています。
検査の負担を軽減するためのAI
動脈からの採血を行うことで、血液中の薬剤の量を測定でき、PET検査で撮影した画像と合わせてより正確な体内の機能を計測することができます。しかし検査中の長い時間、腕などを動かさずに固定する必要があり、患者にとって大きい負担になります。
そこで、PET画像から血液中の薬剤の量をAIで予測する研究が行われています。AIで血液中の薬の量を予測することができれば、動脈からの採血を省略でき、検査による患者への負担を大きく軽減できることが期待できます。
AIによる画像復元技術
PET検査の画像は、注射する薬剤の量が少ないと不鮮明になります。少ない薬剤で撮影した不鮮明な画像を鮮明にすることができれば、薬剤による被ばくを減らすことができ、AIによる画像復元技術が活用されています。
また、通常AIを作る際は大量のデータの学習が必要ですが、ディープイメージプライアー(deep image prior)という画像復元技術を使うと、データが少なくても、学習したのと同じように画像復元をすることができます。新しい薬剤を使った場合や、珍しい疾患に対する検査など、過去データが少ない検査にも使えるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

秋田県立大学 システム科学技術学部 経営システム工学科 准教授 松原 佳亮 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
医用画像工学、医用システム、核医学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
