腹をぐーと鳴らす薬? 新タイプの胃腸薬と「腹の中の脳」の研究
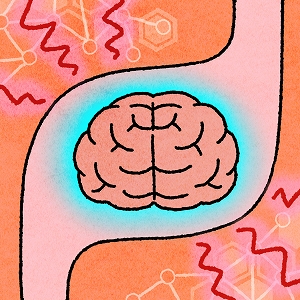
副作用の少ない胃腸薬を
消化管(胃腸)の働きには迷走神経が関係しています。そのため今の胃腸薬の多くは、迷走神経に作用して胃腸の働きを抑えたり促進させたりしています。ただ、迷走神経は体全体の働きに関わることから、それらの薬には「口が渇く」「脳や循環器に影響する」などの副作用があります。そこで、より優れた「胃腸だけに作用する、副作用の少ない創薬」をめざして、胃腸に関する研究が進んでいます。
「腹がぐー」を起こすペプチド
空腹時に腹が鳴るのは胃腸が収縮しているせいですが、胃腸にはその収縮を起こす「モチリン」というホルモンが存在します。ホルモンは、それを受け止める細胞の「受容体」にくっつくことで作用を起こすので、「モチリン受容体」にくっつく物質を作れば、胃腸のみに働く薬が実現する可能性があります。
また、消化管のホルモンの多くは「ペプチド(アミノ酸が数個から数十個つながったもの)」でできており、口から飲むと患部に届くまでに消化・分解されてしまうという問題があります。そこで、最近では「ドラッグデリバリーシステム」といって、カプセルに包むなどして分解されずに患部まで薬を届けられる方法の開発が求められています。そのため薬の材料はカプセルに包みやすい、小さなペプチドが理想とされています。
そこで、モチリン受容体にくっつくペプチドを探して実験を重ねた結果、特定のアミノ酸を7個つなげたペプチドを動物の消化管を切り出した組織に与えると、モチリンと類似の収縮が起こることがわかりました。
腹の中にもう一つの脳?
胃腸の働きを起こす仕組みについては、実はまだ詳しくわかっていません。脳からの指令もあるものの、消化管の周りに張り巡らされた神経系に自律的な命令系統があり、これを「腹の中の小さな脳」として、そこからの指令で胃腸を動かしているのではないかと考えられるような研究結果もあります。こうした消化管の神経系の研究やペプチドの探索などから、全く新しいタイプの胃腸薬が生まれようとしています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

東京都市大学 理工学部 医用工学科 講師 小林 千尋 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
細胞生物学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

