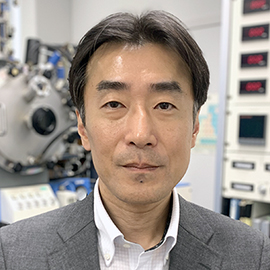「究極の低温」で現れる物質の新しい姿

磁性の観点から新しい物質の性質を見極める
物性物理学の中で、「磁性物理学」は、物質の磁気的な性質、例えば、磁石としての性質などを研究する分野です。新しい磁性物質を作ること、そしてその性質を精密に測ることが研究のポイントです。磁性を持つ元素には、鉄やニッケル、コバルトなどの遷移金属と、希土類(レアアース)があり、これらをほかの元素と組み合わせて新しい物質を作ります。作った物質は、極低温まで冷やして性質を詳しく調べます。-273度の絶対零度近くまで冷やすと、物質の中の原子の熱振動によるノイズが減り、電子の振る舞いがよく見えるようになります。このようにして、磁気相転移や超伝導のような、「電子が主役」となる量子状態を観察できます。
交差する電場と磁場
従来、電場と磁場に対する物質の応答は、それぞれ別なものとして考えられていました。しかし、最近になって、例えば電場をかけると磁石になったり、逆に磁場をかけると電気的な性質が変化する物質が見つかっています。このような性質を「交差相関」と呼び、その現象の鍵を握るのが「多極子」です。多極子とは、原子の中の電子やスピンの分布によって生じる状態のことで、四極子、八極子などの総称です。多極子の存在により、物質は外からの場に対して、予想もしなかった多彩な応答を示すことが期待されます。
未来を拓く新しい物質の探索
交差相関の発見により、多極子を持つ新しい物質の探索と研究が盛んに進められています。例えば、原子中の電荷が4つの極をなす電気四極子が、結晶中で交互に並ぶ現象が見つかっていて、その中で超伝導が起きることが観測されました。交差相関の研究が進むことで、将来的には、電気で磁石の性質を制御したり、磁場で熱勾配を生み出したりする新しい技術が生まれるかもしれません。
物質を高温で溶かして化合物を作り、極低温に冷やして磁性を調べるという実験を通じて、私たちの想像を超える物質の姿が少しずつ明らかになってきています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )