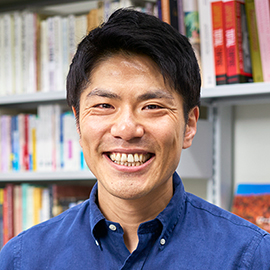全国の小学校に配布された天皇の写真 その歴史から読み取れること

国家意識の醸成に不可欠な義務教育
近代国家は多種多様な、お互いに直接面識のない人々の集まりです。国家が集団として機能するには共通の価値観や考え方の形成が不可欠であり、多くの国では義務教育がその役割の一端を担ってきました。1892年から米国の小学校で始まった「忠誠の誓い」(児童が星条旗に向かって米国への帰属を宣言する儀式)は、英語を話さない移民の流入に不安を覚えた国家指導者たちが導入した政策で、それは異なるルーツを持つ人々をアメリカ人に仕立て上げる装置でした。
天皇を中心に据えた日本の学校教育
同じ頃日本では、1890年に国会が開設されるなどして国民の声が国家政策に反映される仕組みづくりが進行していましたが、政府の一部の人々は、民主化によって世論が制御不能に陥る可能性を危惧していました。それを防ぐ目的で、義務教育を通して若い世代に天皇への忠義という共通の価値観を醸成する政策が生まれました。その具体的な方法の一つが、天皇の肖像写真を小学校に配り、天皇の誕生日などにそれを生徒に拝ませるというものでした。
学校教員にのしかかる責任
その結果、1920年頃までには、ほとんどの日本人は天皇を国家を象徴する特別な存在として崇めていました。そして、当初は比較的貴重な複製物としか捉えられていなかった天皇の写真も、何があっても保護されるべき神聖な物とみなす考えが主流となりました。
その保護責任は教師に託され、もしも日々の保管方法が杜撰で写真を傷めてしまったり、学校火災でそれを焼失した場合、政府は責任のあった教員を処分し、メディアは実名で批判しました。そのようなバッシングは、写真、またそれが示す天皇は神聖であるという考えをより強固なものにしていきました。
1940年代に日本各地が空襲を受けるようになると、戦火から天皇の写真を守ろうとして死亡した教員が多くいました。これら現象は単に戦争の悲劇として片付けるのではなく、日本の近代国家構築の帰結として捉えることで、より深い理解ができるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報