集中すると雑音が聞こえないのはなぜ? 音の認識を調節する仕組み
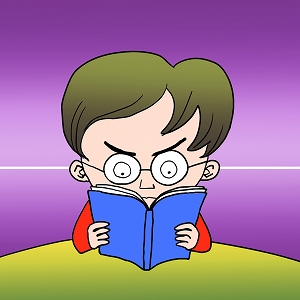
必要な音を脳が取捨選択
パーティー会場のようなざわざわした場所でも、自分の名前など興味のある言葉はクリアに聞き取れることがあります。これを「カクテルパーティー効果」といいます。また、何かに集中しているとき、部屋の空調の音は聞こえなくなります。これらは、耳に入るいろいろな音の中から、脳が必要な情報を取捨選択しているのです。これを「感覚ゲーティング」と呼びます。
音を認識するのは、脳の「聴覚皮質」という部位です。耳から入った音の情報が「視床」という部位に到達すると、神経細胞の興奮が起こり、「活動電位」と呼ばれる電気信号が生まれます。この信号が、神経細胞から長く伸びた「軸索」と呼ばれる突起部分を伝わり、たくさんの神経細胞が耳から視床までの情報を聴覚皮質までリレーのように信号を届けます。
伝えるべき信号を調節
聞き取る音の取捨選択は、脳の注意機能を担っている「前頭前野」という部位からの「トップダウン」の指令と、耳→視床→聴覚皮質という「ボトムアップ」のルートで必要な情報の取捨選択をしていることが、近年の研究でわかってきました。
それに関わっているのが、神経伝達物質である「アセチルコリン」です。視床の神経細胞の軸索経路にアセチルコリンの受容体が見つかり、そこで電気信号の調整をしていると考えられます。視床からの信号が正確に、また選択的に聴覚皮質まで伝わるには、複数の神経細胞が同時に興奮・発火する「同期」という現象が必要です。アセチルコリンはタイミングがずれたノイズの高い電気信号を「同期」させて、意味のある信号に変えることで調節をしているのです。
新たな治療法に結び付くか
最近の研究では、音の周波数が特異的にアセチルコリンを放出する細胞に働きかけて、アセチルコリンを聴覚皮質に放出させるという報告もあります。このような聴覚系の仕組みに関する研究は、統合失調症における幻聴や自閉スペクトラム症における聴覚過敏などの病気に対する、新たな治療法の開発に結び付く可能性があると期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

創価大学 理工学部 生命理工学科 教授 川井 秀樹 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
神経生物学(神経生理学)先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

