人工衛星が明かす雨雲の秘密
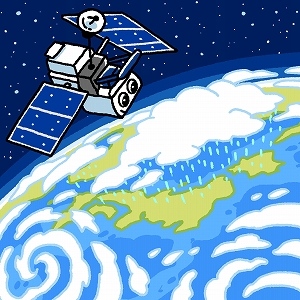
雲の中をのぞく宇宙の目
雨や雪が降るメカニズムを明らかにするには、雲の中を見ることが必要です。これを実現したのが、雲の中の雨や雪を立体的にとらえられるレーダーを搭載した「全球降水観測計画(GPM)主衛星」です。地上から上空に向けて測定する従来のレーダーとは違い、GPMは上空から地表へと雲の立体構造を把握できるのです。90分で地球を一周し、太平洋の真ん中や南極付近など、地上観測が困難な場所でも均一な精度で降水を測定できます。これにより、世界中の降水の様子を、同じ条件で比較できるようになりました。
発達した積乱雲=豪雨?
私たちは、積乱雲が高く発達すると強い雨が降ると考えがちですが、人工衛星の観測結果は、それが必ずしも当てはまらないことを示しています。上昇気流が強く雲が高く発達していても、大気中に含まれる水蒸気の量が少ないと、雨粒の材料そのものが不足してしまい、地上に届く雨はそれほど強くならないことがあります。反対に、上昇気流がさほど強くなくても、水蒸気が豊富な状態では、雲の中で雨粒が効率よく育ち、大粒になって地表に落ちてくるため激しい雨になることがあります。このような仕組みが明らかになったのは、レーダーを搭載した人工衛星によって、雲の中のどの高さにどれだけの雨があるかを立体的に観測できるようになったからです。
人工衛星データが拓く気象学の新時代
気象衛星「ひまわり」は、以前は1時間に1回しか観測できませんでしたが、現在は2分30秒ごとに観測できるようになりました。積乱雲の寿命は1時間未満なので、この高頻度観測によって、雲の発達過程をほぼリアルタイムで追跡できるようになりました。
人類は古くから雨や雲の存在を知っていましたが、その内部構造を世界共通の視点で観測できるようになったのは、ここ10年ほどです。衛星観測データを活用することで、気象現象の理解がさらに深まり、予報精度の向上や極端な気象現象への対策に貢献することが期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
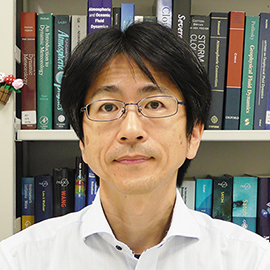
富山大学 都市デザイン学部 地球システム科学科 准教授 濱田 篤 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
気象学、衛星気象学、大気物理学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
