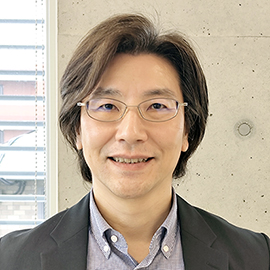自然な環境で快適に暮らす、環境共生建築
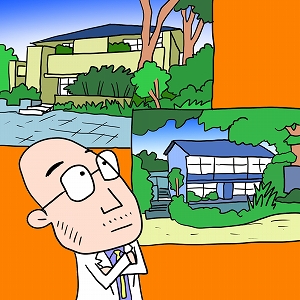
自然の変化に対応する体
現代の建築では、照明や空調設備が完備され、常に室内環境が調整されています。しかし、明るさや温度が自然環境と切り離された状態が、人の健康に本当に良いと言えるでしょうか? 人の体温や感覚は、時間や季節によって変化します。つまり、本来の人の体は、ゆらぎのある自然の変化に対応できるようにつくられているのです。温度や明るさの変化がほど良くある環境の方が、体にとって自然だと言えます。例えば、外気温が上がり始める夏前に少し汗をかくような環境に身を置くことで、体が夏モードに切り替わり、体温調節機能がしっかりと働くようになります。
自然と共に暮らす建築
こうした考え方をもとにしているのが「環境共生建築」です。これは、建物の形状、断熱性能、窓の配置などの工夫により、自然の力を取り入れながら快適な室内環境をつくる建築のあり方です。例えば、日本の住宅は天井の中央に照明器具を一つ設置して全体を明るくするスタイルが一般的でしたが、最近では「多灯分散照明方式」が提唱されています。これは、複数の小型電灯を分けて配置し、時と場所に応じて明るさを自由に調整する仕組みです。太陽光が届かない場所には補助的に照明を使うことで、自然な明るさが得られ、かつ省エネルギーにも貢献します。また、天井面を照らすと部屋全体が明るく感じられる効果があることから、照明を上向きにするといった工夫もなされています。
建築がつなぐ自然と人
かつての日本の住まいでは、季節に合わせて空間の使い方やしつらえを変えていました。夏になると、窓に「すだれ」をつるしたり、床に「ゴザ」を敷いたりすることで、涼しさを工夫していたのです。このように、人が自然と積極的に関わりながら暮らしをつくっていくことが、豊かな住環境につながります。スイッチ一つで均一な環境をつくる便利さも大切ですが、もう一度、自然の変化に目を向けて、それを受け入れながら暮らす建築のあり方を考えてみる必要があるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。