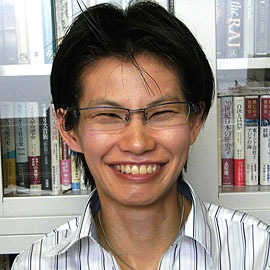1930年代、綿をめぐる貿易摩擦と日本

日本・インド・イギリス、三国の争い
インドがイギリスの直轄領になったのは、1858年。それ以来、インドはイギリスの綿製品にとって重要な輸出市場でした。しかし1920年代末から1930年代初めにかけて、日本の綿製品が急激にインド市場に進出し始めました。当時のインド市場は、約8割を国産品が占めていて、あとの2割をめぐってイギリスと日本がシェア争いをしていました。ほぼ同時期、1932年にイギリス帝国特恵関税制度が確立され、イギリス帝国内で流通する製品について、帝国の製品には低い税率の関税を、日本やアメリカなど帝国域外国の製品にはより高い税率の関税がかけられることになりました。1930年代、このような状況下で日本・イギリス・インド三国間の交渉が繰り返されることになります。
綿をめぐって初めて国際的貿易摩擦を経験
日本はインドに綿製品を輸出する一方、インドから綿花を買い、お互いが顧客でもありました。その関係から、30年代初めに、日本の綿製品がすごい勢いでインドに輸出された時、インドは日本製品にかける関税率を一時期75%まで上げ、腹を立てた日本が、インド綿花を買うのをやめる、という対抗措置をとりました。当時、日本はアメリカからも綿花を輸入し始めていたので、日本がインド綿花を買わなくなったらインドは困ります。ところが、インド・ボンベイ(現ムンバイ)の綿業資本家はこの日本との事態をイギリスの綿業資本家との交渉で武器として使いました。もし、イギリスが日本の代わりに綿花を買ってくれるのなら、イギリス製品に対する税率引下げに賛成してもいいという取引をするのです。もしイギリスが買わないと、インドには痛手になるので、日本に対して、日本の言う通り関税率を下げざるをえなくなり、イギリスは困るだろうという巧みな駆け引きでした。綿をめぐる三国間の交渉は何度も行われ、この綿問題は、日本にとって初めて経験する国際的な貿易摩擦で、世界の中で経済活動をする難しさを知った出来事でした。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報