数学で脳をつくる
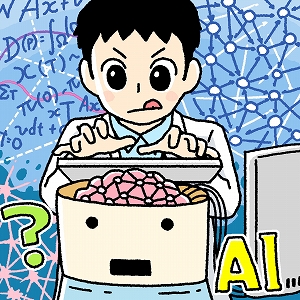
脳はAIよりも柔軟で、しかも省エネ
人工知能(AI)は、人間の脳のしくみをヒントにつくられています。しかし実際の脳は、AIよりもはるかに複雑で柔軟性があり、しかも圧倒的に省エネです。例えば、生き物の脳は体の運動を巧みに制御したり、視覚や聴覚など複数の感覚を統合して情報を処理します。これらは、現在のAIにはまだ難しいことです。そこで、脳の情報処理のしくみを数学的に表現し、理解することで、脳の優れた性質を取り入れた新しいAIの構築が目指されています。
脳の数理モデルをつくる
脳の情報処理を数学的に表すには、対象の時間的な変化を記述できる「非線形ダイナミクス」という数学の手法を使います。この手法により、神経細胞1個の動きは数学的に再現できます。ただし人の脳の場合、約1000億個の神経細胞がそれぞれ別の1万個の神経細胞とつながる複雑なネットワークを形成しているため、計算は容易ではありません。
そこで一つのアプローチとして、数百の神経細胞からなる「小さな脳」について考えます。神経細胞が数百あれば、音声認識などのパターン認識、運動制御などが可能です。神経細胞のいろいろなつながり方を仮定して数学的に表現し、どのように情報処理が行われるのかを検証します。こうしたモデルを解析することで、脳の活動やはたらきへの理解が深まり、新しいAIの可能性を探ることができます。
「リザバーコンピューティング」という発想
こうした脳のモデルづくりに重要なのが「リザバーコンピューティング(リザバー計算)」という機械学習の手法です。これは、「多数の非線形素子が結合したシステム」のことです。神経細胞をはじめ、自然界の多くのシステムは非線形素子と見なすことができるため、この手法が使われます。例えば、聴覚に関わる細胞と視覚に関わる細胞の動きを情報に変換し組み合わせて処理すれば、マルチモーダル(多感覚)なモデルをつくることができます。さらに、周囲の環境に応じて学習し、行動を変化させるようなロボットへの応用も期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
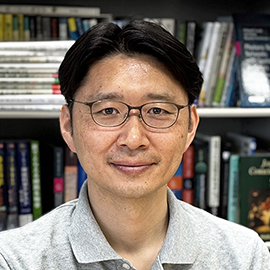
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?






