「社会連携」から生まれる、人の暮らしと人生を支える新しい医療

医療×地域社会の連携が生む新しい価値
チーム医療を病院の外で行うことを「連携」といいます。在宅での医療・介護を支えていくには、多機関・多職種の連携が欠かせません。医師を中心として看護師、介護士、栄養師などさまざまな人々が集まってコミュニティを作り、関係を深めることで地域医療の提供を円滑にしています。今、「医療や介護だけでは、人の暮らしや人生を支えていくことは難しい」と気づいた人々が取り組み始めているのが、地域の民間企業やさまざまな専門分野の人々と手を結ぶ「社会連携」です。医療×地域社会の連携で、単独では得られない新しい価値を生み出しています。
人の暮らしと人生を支える挑戦
のどにつまりにくい餅、とろみがあって舌の上で味わえる酒などは、食べ物を飲み込む力が弱まる「嚥下(えんげ)障害」があっても食べる楽しみを持てるようにと、医療従事者が食のプロに呼びかけて開発された嚥下食です。嚥下食で作られた懐石料理の試食会に、脳梗塞を患ってから食べることが難しくなった妻と、介護者の夫が訪れました。おいしい、おいしいと食べる妻を見守っていた夫は、「ごちそうさま」の声を聞くなり号泣し、「食事の時間は私たちにとって苦痛でした。またこんな時間が持てるなんて」と声を震わせました。飲み込みやすい嚥下食、おいしい懐石料理だけでなく、「もう二度とないとあきらめていた、夫婦で食事を楽しむ時間」を提供できたのです。
進んでいる医療って、どんな医療?
AI診断やロボット手術は最先端の医療ですが、それだけが進んだ医療でしょうか。ある病院は「また来てねと言える病院」をめざして、地域の人々の居場所づくりに取り組んでいます。病院と自治体とが協力して公園を作ったり、地元の商店街でカフェを運営したりする「病院まちづくり」も始まっています。病院と地域社会の連携も、人々の暮らしと人生を支える「進んだ医療」の形です。今後はもっと、人々の暮らしやまちの方へと近づいていく医療が増えるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
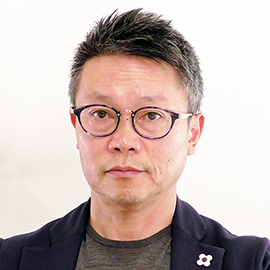





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
