雪が支える水の循環 自然と工学が創る未来

世界が驚く日本の積雪水資源
日本は、国土の50%が豪雪地帯に指定されており、この雪が重要な水資源となっています。水の循環を解明する「水文(すいもん)学」の研究により、雪の新たな価値が明らかになってきました。特に日本の豪雪地帯は世界でもまれな環境にあります。「温暖積雪域」と呼ばれ、0度に近い環境のために大気中に水蒸気を多く含むことができ、年間4~5メートルもの豪雪をもたらしながら、春になると蓄積された雪がすべて解けて活用されています。より平均気温の低い北欧やシベリアでは、降雪が少なく、水資源として利用できないため、日本のこの環境は国際的な関心を集めています。
自然が作る季節の水タンク
このような温暖積雪域では、独特の貯水システムが形成されています。冬に山に積もった雪は、春から夏にかけて2カ月程度かけてゆっくりと解け出します。これは弱い洪水が長期間続く状態で、この融雪水が米の栽培や発電に利用されています。山で一度蓄えられて、さらにダムで蓄えられるという二段階の貯留により、長期にわたって安定した利用が可能になります。
人工衛星で雪の状況を観測し、コンピュータに自然環境を再現して、数値シミュレーションと組み合わせると、特徴的な日本の豪雪地帯の水循環も再現できます。それにより、効率的な管理や洪水対策の立案が可能です。
地球規模で広がる研究の輪
この積雪水資源の研究は、国際協力を通じて世界の途上国支援にも発展しています。ボリビアやアフガニスタンなど、氷河の水に依存する国々では、温暖化により氷河が縮小し、将来の水供給に不安を抱えています。これらの国の研究者との国際共同研究により、現地の仕組みを解明して、持続可能な都市計画や利用戦略の策定を支援する取り組みが行われています。
途上国では都市部への人口集中が進む中、水道インフラ整備には水資源量の予測が不可欠です。自然科学と工学技術を融合したアプローチが、地球規模の水問題解決に貢献し、研究者育成を通じて持続可能な国際協力を実現しているのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
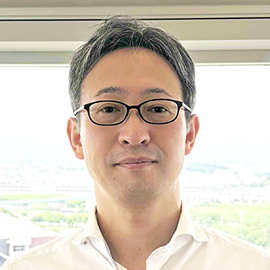





![選択:[SDGsアイコン目標6]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-6-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

