それって本当に当たり前? ことばの不思議を探る
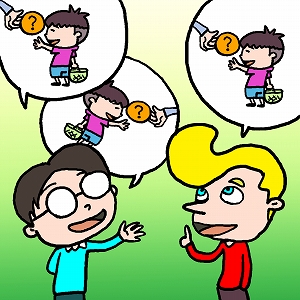
ことばには目に見えない「構造」がある
「先生が生徒をグラウンドを走らせた」。この文は何かがおかしいですよね。何がおかしいかといえば、「を」が2つあることです。では、なぜ「を」が2つあるとおかしいのでしょうか。
私たちが無意識に使っていることばには目に見えない「構造」があり、様々な「操作」が行われています。ことばの構造を探り、何が起こっているのかを研究するのが言語学です。
母語と外国語との共通点・相違点を探る
母語は成長と共に自然に使えるようになるため、母語を意識する人は少ないでしょう。しかし外国語を学ぶ時には「なぜ?」と不思議に思うことが多いはずです。例えば、英語は「What did John buy?」は〇、「John bought what?」は×です。一方、日本語は「太郎は何を買ったの?」「何を太郎は買ったの?」のどちらも○です。英語のwh疑問文では疑問詞は必ず文頭に置かれますが、日本語では疑問詞は文頭になくても許されるのはなぜでしょうか。
この問題は、日本語だけ、あるいは英語だけを観察していたら生じ得ないものです。様々な言語を分析し比較することで、共通点や相違点が見えてきます。なぜ同じなのか、なぜ違うのかを考えながら、「ことばの能力」とは何かを明らかにしていきます。
「当たり前」に疑問を持つ
wh疑問文を学習した時、「元の位置にある疑問詞が文頭に『移動』する」と教わったと思います。受け身文でも目的語が主語に『移動』したと教わりましたよね。つまり、「移動前の文」と「移動後の文」が存在することになります。ではこれらはどこにどのように存在するのでしょうか。そしてなぜ移動が起きるのでしょうか。
このように言語学とは「当たり前」と思われている現象に「なぜ?」と疑問を投げかける学問です。ことばを使えるのは人間だけです。ことばの使い方ひとつで人の評価が変わることもあります。ことばは「心の窓」ともいえます。言語学者たちは、ことばの研究を通して「人間とは何か」を明らかにしたいと考えています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

別府大学 文学部 国際言語・文化学科 教授 藤森 千博 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
言語学、英語学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





