美食のフランス人はなぜ太らない? 「食」から考える社会と政策
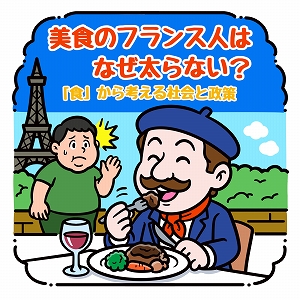
「食」が遺産に
2010年、「フランスの美食術」がユネスコ世界無形文化遺産に登録されました。形のない重要な文化を保護するためのこの制度は、これまで音楽や舞踊を主な対象としてきましたが、ここに「食」という分野を初めて認めさせたのが美食の国フランスでした。なお、この取り組みに倣ったことで後年「和食」も登録されました。
「フランスの食」と聞けば、高級フレンチなどが想起されますが、この登録は料理そのものの味や技術が対象ではありません。フランス人が大切にしてきた、食卓でのコミュニケーションや食事を楽しむ方法が対象であることが重要なのです。
食文化と健康
フランス人は一日3食を決まった時間にとるため、間食が少なくなる傾向があります。また、一度の食事にじっくりと時間をかけます。これが、食卓を分かち合う家族や友人、地域の人たちとのコミュニケーションを深める役割を果たしてきました。また、時間をかけることにより健康面でも消化の負担が軽減され、品数が増えることで栄養バランスが整いやすくなります。食事におけるタンパク質・脂質・炭水化物のバランスを表す「PFCバランス」で見れば、フランスの食事は概して脂質が多いものです。しかし、同程度に脂質の多い食事をとるアメリカ人と比べると、国民の肥満率が非常に低くいのは、フランスの食文化が深く関係しているのです。
政策と社会
とはいえ、グローバル化の進展によってフランスの食文化が変化し、肥満が増えてきたことから、フランス政府は2000年頃に健康・栄養政策を打ち出しました。そうした経緯があり、「食」を打ち出すにはマイナス要素もなくはない中で、政府はそれまでにない「食」の分野で「フランスの美食術」を文化として申請したのです。
このように、フランスに限らず世界各国で打ち出される政策は、そこに暮らす人々の文化や歴史、風土と切り離すことはできません。それらを丁寧に観察し、長い時間をかけて育まれてきた社会のシステムと照らし合わせるように分析する姿勢が重要なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )





